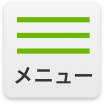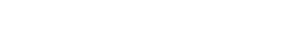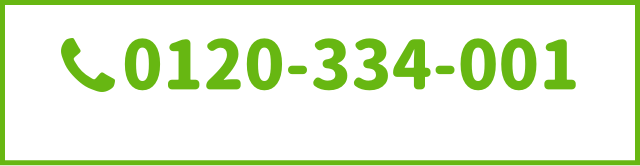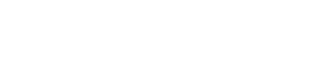借金の時効が成立する条件と、時効の援用ができないケース

「長期間返していない借金があって、相手方からも音沙汰がない」
このような場合は、時効で借金がなくなるのではないかと期待する方もいらっしゃるでしょう。
確かに、借金にも消滅時効は存在します。
しかし、長期間放置されていればそのまま返さなくて済むようになるわけではなく、成立の条件を確認した上で、正しいやり方でそれを債権者に主張しなければなりません。
今回は、借金の時効で実際に借金を帳消しにできる可能性と、できなかった場合の対応方法をわかりやすく解説します。
1.借金の時効は何年?
借金の時効は、民法で定められています。
なお、消滅時効については2020年4月1日から施行された改正民法により「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」で時効と変わりましたが、現状時効が成立する期間に該当するケースでは改正前の民法が適用されますので、以下では改正前の民法に沿って解説いたします。
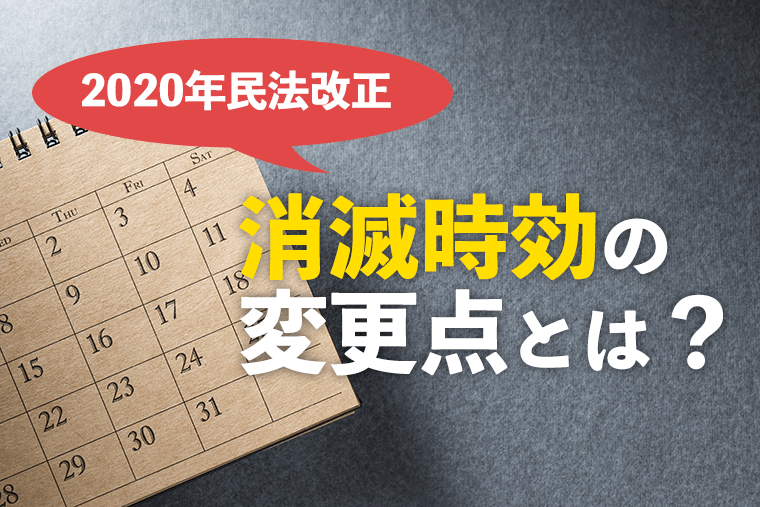
[参考記事]
2020年の民法改正による消滅時効の変更点とは?
改正前の民法第167条1項で、債権は「10年間行使しないときは消滅する」と定められています。
つまり、原則10年間、債権者が権利を行使しない場合は時効を迎えます。
ただし、消費者金融のキャッシングやカードローンなど、貸金業者からの借金については、商法522条によって、時効は5年と定められています。
貸金業者はお金を貸すことを商売で行っており、多くの取引を迅速に処理すべき立場であることから、商法で特別に定められているのです。
この期間は、お金を借りた日から数えて5年または10年ではなく、最後の取引日(最後の返済日や最後の借入日)から数えて5年または10年経過している必要があります。
滞納をしている人に対し、業者が「少額でも払ってください」などと言うのは、お金を少しでも返してほしいということ以外に、支払わせることで時効のカウントを振り出しに戻すためなのです。
2.時効の援用
上記の期間を迎えたとしても、自動的に借金返済義務がなくなるわけではありません。
借金をなくすには「援用」の手続きが必要です。
-
(1) 時効の「援用」とは?
借金の消滅時効は、お金を借りた人が「援用」という意思表示をすることで効力を生じます。
これは民法145条に定められており、時効の援用をしない限り、借金が消えることはありません。時効の援用の方法については、以下のコラムで詳しく解説しています。
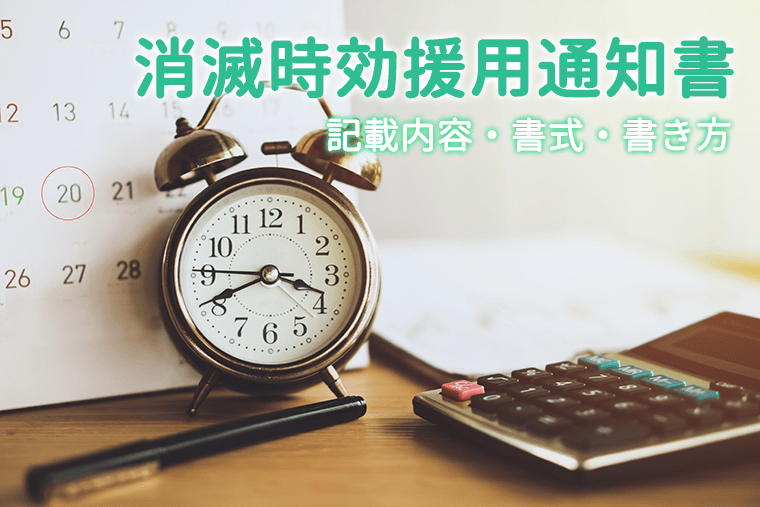
[参考記事]
消滅時効援用通知書の記載内容・書式・書き方について
-
(2) 時効を援用する条件は?
借金の時効は「更新」をすることも可能です。
時効の更新は民法147条に定められており、更新事由がある場合は、その時点から再度カウントされることになります(改正前民法における「中断」です)。時効の更新には、以下の3つの手続きがあります。
逆に言えば、以下に当てはまらないことが、時効を援用できる条件と言えます。①請求
「請求」とは、債権者が債務者に対してその権利内容を主張する裁判上及び裁判外の行為を言い、具体的には「裁判上の請求」がこれに当たります。
「裁判上の請求」は、裁判所に訴訟を提起する「訴訟」がその代表例です。
他にも、債権者が契約書などの証拠・書類をそろえて簡易裁判所に提出し、裁判所が債権者に代わって債務者に支払い命令を出す簡易的な手続き「支払督促」も該当します。また、貸金業者が「お金を返してほしい」と裁判外で請求することを「催告」と言い、催告をしてから6ヶ月間時効期間を延長することが可能となります。
催告はあくまでも暫定的な措置なので、時効の更新をするにはその6ヶ月間に、新たに裁判上の請求などをする必要があります。
②差押え、仮差押え又は仮処分
債権者が債務者の財産を差し押さえ、または仮差押えしたときには時効が更新します。
例えば、住宅ローンの滞納により、自宅が差し押さえられたときは、競売開始決定が債務者に送達された時、またはその前に競売開始決定の登記がされた時に時効が更新します。

[参考記事]
仮差し押さえされたらどうすれば良いか?
③承認
承認は、借金をしている人が貸してくれた人に対して、借金を負っている事実を認識していることを示すことです。
承認は会話だけでなく、借金があるがゆえにとった行動も含めるので注意が必要です。特にありがちなのは、返済による更新です。僅かな額でも返済をすると、借金があることを認識しているとみなされるので、その都度時効は更新します。
毎月返済している場合は毎月更新していることになり、時効は最終返済日からのカウントとなります。また、仮に時効を迎えていることを知らずに、債権者と話し合いの中で「少しでも返す」とか、「返済を待ってほしい」といった、債務を認める発言してしまうと、これも「承認」と見なされ、時効を主張できなくなることがあります。
そのため、随分昔に借りたお金があり、時効を迎えている可能性がある場合は、債権者と話す前に弁護士など専門家に相談をしましょう。
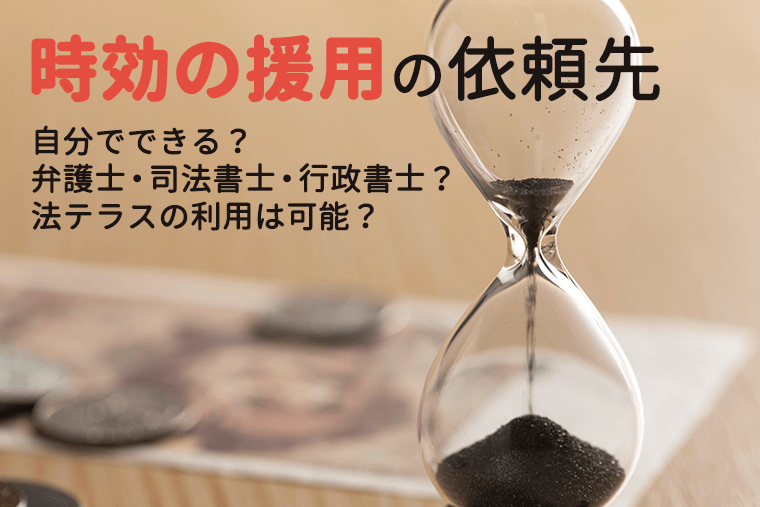
[参考記事]
時効の援用のおすすめ依頼先|弁護士・司法書士・法テラス・自分で?
-
(3) 実際に借金の時効を成立させるのは難しい?
貸金業者からの借金は5年で時効を迎えますが、実際には援用の条件を満たして時効で帳消しにすることは難しいです。
キャッシングやカードローンを滞納すると、電話や書面で督促が行われます。3ヶ月以上滞納が続くと取り立ては激しくなり、それでも返済がない場合は時効の前に裁判上の請求がなされることが少なくありません。
業者は貸金業のプロフェッショナルですので、時効の更新についても心得ており、そろそろ時効を迎えるな、という時点で時効更新の手続きを行います。
つまり、貸金業者からの借金を返せないとき、時効によって借金を帳消しにすることは、かなり難しいといえます。仮に夜逃げをしたとしても、新しい土地での住民登録もままなりません。5年もの間、督促のプレッシャーやブラックリストへの掲載に耐え、債権者から逃げ続けるのは至難の業です。
3.時効を待たずに借金を解決する「債務整理」
では、借金を完済できず、時効の援用もできない場合は、どうしたら良いのでしょうか?
その場合は、「債務整理」をすることを検討しましょう。
債務整理は返済に困っている人を救済するための制度で、 時効を待つことなく借金を減額、または帳消しにすることができます。
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、弁護士に相談をすればそれぞれの状況に応じてベストの方法をアドバイスしてくれます。
もちろん、弁護士ならばあなたの借金についての時効の成立条件を確認してくれて、援用が可能ならばその手続のサポートも受けることができます。
時効を援用すること自体にデメリットはありません。しかし、自分では「時効の期間が過ぎている」と思っていても、途中で更新されたため実際には時効は成立していない、ということがあり得ます。
このような時に自己判断で手続きを進めると、援用ができないだけでなく、相手方に自分の居場所を知らせてしまうだけになり、せっかく成立しかけていた時効のカウントが更新してしまう危険もあります。借金問題は一度弁護士にご相談ください。
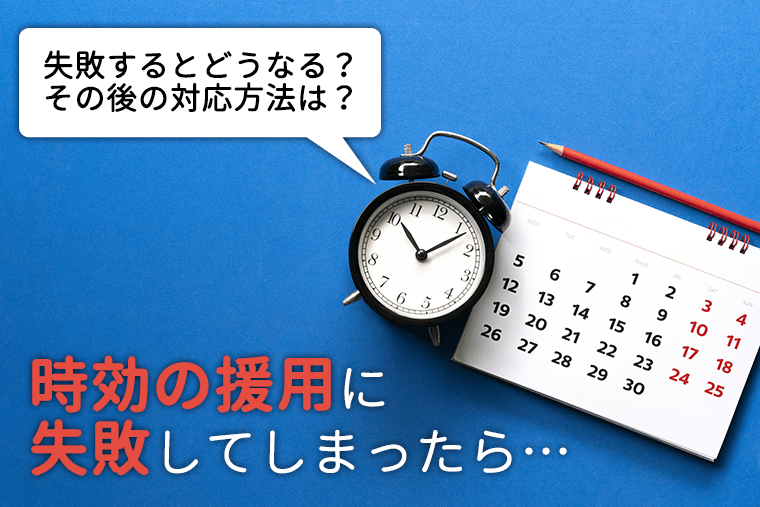
[参考記事]
時効の援用を自分でやろうとして失敗してしまったら…
4.自己判断の時効の援用はデメリットが多い!
借金(特に業者からの債務)を時効により帳消しにするのは、法律上は可能でも、現実的にはかなり難しいです。
実際に長期で返済していない借金がある場合はともかく、時効成立には遠い借金がどうしても返せない場合は、時効を待たずに債務整理をすることをお勧めします。
泉総合法律事務所は、債務整理に力を入れている弁護士が多く在籍し、解決実績も豊富です。
債務整理の相談は何度でも無料ですので、お困りのことがあればどうぞお気軽にご相談ください。