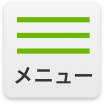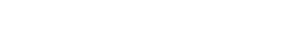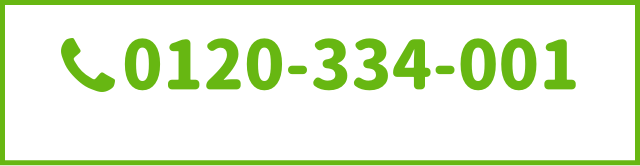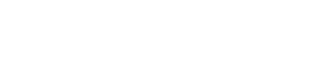熟年離婚後の老後破産対策|財産分与・慰謝料請求

厚生労働省の調査によると、結婚後20年以上の「熟年離婚」の件数は年々増えており、2020年には離婚カップルの5組に1組以上(21.5%)が熟年離婚です。
しかし、実はその後の生活を考えて、熟年離婚を躊躇している方も多くいます。
「熟年離婚して幸せになりたい!」と思っても、離婚後の収入への不安や、子供・親族に金銭的迷惑をかける可能性を思うとなかなか踏み出せないのです。
今回は、熟年離婚を考えている方に向けて、その後の生活の展望や資金作りの方法について解説します。
1.熟年離婚の現状
熟年離婚とは、年齢に関係なく、結婚して20年以上経つ夫婦が離婚をすることです。
熟年離婚の引き金になる理由は多岐に渡ります。
価値観の違いや性格の不一致から相手が家にいることにストレスを感じてしまったり、モラハラやDVが発生したり、見て見ぬふりをしていた不倫(異性問題)について子育て終了後に揉めるケースもあります。
さらに、舅・姑と合わない、相手の親の介護が苦痛(介護離婚)というケースもあるようです。
このように、結婚生活はその長さに比例して我慢や忍耐を強いられることも増えるので、離婚を切り出したときには修復不可能なレベルの溝ができていることも珍しくありません。
しかし、熟年離婚した後はバラ色の人生が待っているとは限らず、の孤独感や寂しさから離婚を後悔することも多いです。
さらに、離婚するまで専業主婦だった人は、いざ働こうにも職探しに苦労をすることになります。条件のよい仕事に恵まれなければ、収入は厳しいものになります。
熟年離婚については見切り発車で踏み切ることなく、離婚後の資金も考え、慎重に判断していく必要があるでしょう。
2.熟年離婚後のお金の心配を解消する方法
熟年離婚の最大の問題は、離婚後の生活です。実際に見切り発車で熟年離婚に踏み切ると、特に女性側はお金の心配が尽きず、精神的にも負担が大きくなります。
そうならないために、もしどうしても熟年離婚をしたいと考えている方は、以下の方法で少しでも離婚後の資金を得ておくとよいでしょう。
(1) 慰謝料請求
離婚に至る過程で相手に落ち度がある場合は、慰謝料を請求することができるかもしれません。
慰謝料を請求できるケースとそれぞれの相場は以下の通りです。
①身体的・精神的暴力があった(DV・モラハラ)
身体的暴力・精神的暴力は離婚原因となります。この場合の慰謝料相場は50万~300万円です(身体的暴力があった場合はこれより高くなるケースがあります)。
DVやモラハラが原因で離婚する場合は、日々の暴力や暴言を記録したり、会話を録音したりしておくことが大事です。
また、病院の診断書などもあれば証拠として提出することができます。
このような証拠を持ち、離婚問題に強い弁護士に慰謝料請求について相談に行くことをおすすめします。
②相手が不貞行為を働いた
相手が不倫・浮気をしている場合の慰謝料は、50万~300万が相場です。
単なるデートや食事では不倫にはならず、実際に肉体関係があったことが必要です。
不貞行為を立証するには、LINEなどスマートフォンでのやり取りのほか、クレジットカードの利用明細やラブホテルの領収書などが有力な物証となります。
また、配偶者との会話の録音や、探偵の調査報告書なども証拠となります。
③悪意の遺棄
悪意の遺棄にあたるケースは多岐にわたります。
例としては、理由もなく家に帰らない、生活費を入れない、専業主婦(主夫)または共働きなのに家事を一切放棄する、といったことが挙げられます。
こうしたことが原因で離婚をする場合の慰謝料の相場は、50万~300万円です。
【慰謝料請求の時効】
慰謝料の請求ができるのは、離婚後3年以内です。つまり、離婚した日から3年を過ぎると時効になるので注意が必要です。ただし、不倫や浮気、DVから3年以上経過していても、離婚から3年以内であれば慰謝料は請求できます。
また、この期間中に裁判をおこせば時効は中断されるので、結論が出るまでに3年経過しても問題はありません。
また、離婚から3年以内に何らかのアクションを起こすことが難しい人は、内容証明で慰謝料請求することで時効を6ヶ月間猶予することもできるので、離婚に際して慰謝料をもらっていない人は、早めに弁護士に相談をしましょう。
(2) 財産分与
離婚の際の財産分与も資金確保の重要な手段です。
しかし、財産を分けるといっても、互いの財産を丸ごと半分にするわけではありません。
財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚期間中に協力して取得ないしは維持した財産のみです。個人が独身時代に得た財産は対象になりません。
また、マイナスの財産も分与の対象となるので注意が必要です。
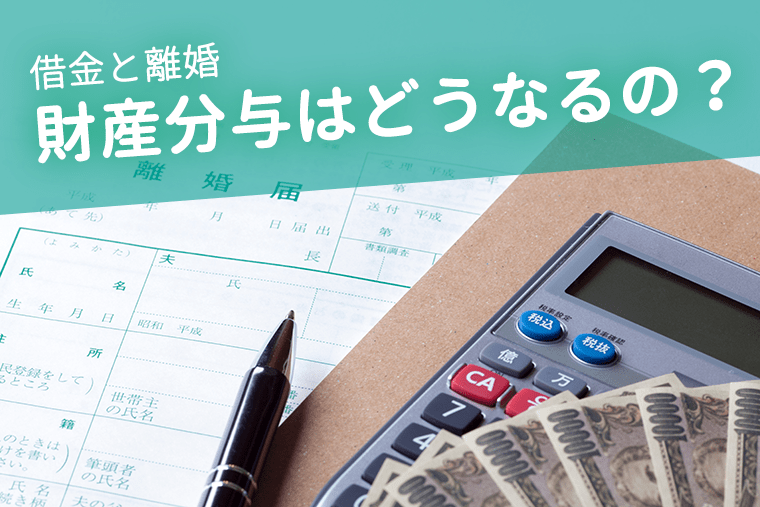
[参考記事]
借金がある場合の離婚|財産分与はどうなる?
財産分与の割合は夫婦の話し合いで自由に決められますが、2分の1ずつとなるケースが多いようです。一方で、収入の関係からか7対3で夫側の割合が多くなることもあります。
財産分与の割合が話し合いで決着がつかない場合は、弁護士に依頼をするか、家庭裁判所に対して調停または審判の申立をすることをお勧めします。
なお、以下のようなものも財産分与の対象となります。
①退職金
配偶者の退職金も財産分与の対象となります。
退職金分与の割合については、夫が退職金をもらうまでに、妻がどれくらいの貢献をしたのかという点が考慮されます。
判断のポイントは夫婦の婚姻年数や、夫の勤続年数などを基準にして計算します。
②年金
熟年離婚では年金分割も大きな収入源となります。実行に際しては夫婦で分割することと、分割の割合の合意が必要です。
分割割合は2分の1が上限で、それ以上の割合を請求することはできません。
なお、専業主婦で会社員や公務員に扶養されている配偶者だった人は3号分割制度が適用されます。
3号分割は平成20年5月1日以後に成立した離婚が対象で、この場合は相手の合意は不要で、分割割合は2分の1に固定されています(自営業者の妻には適用されません)。
年金分割については、細かくルールが定められているので、詳しくは最寄りの年金事務所に問い合わせをすることをおすすめします。
3.まとめ
現在、老後破産という言葉が頻繁に使われています。熟年離婚をきっかけに老後破産に陥ってしまうというケースも決して少なくありません。
熟年離婚を考えるならば、慰謝料請求、財産分与などが重要になり、弁護士を介した手続きが有効です。
また、離婚が原因で借金などが嵩み生活が厳しいといった場合にも、債務整理に強い泉総合法律事務所の弁護士であれば、必ずやお力添えできると自負しております。
決してお悩みを一人で背負い込まないでください。
借金問題のご相談は何度でも無料ですので、ご遠慮なくお問い合わせいただけたらと思います。