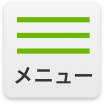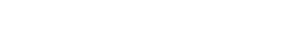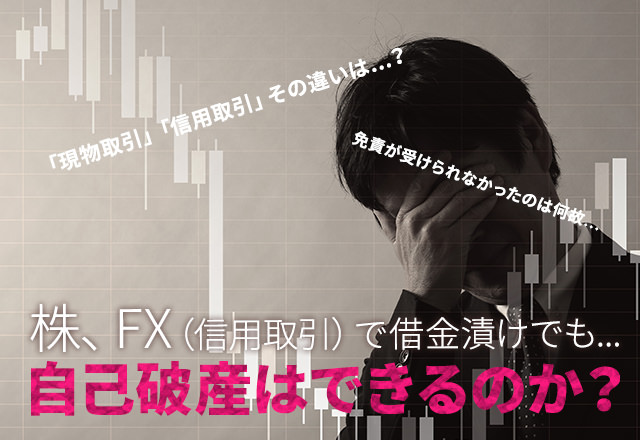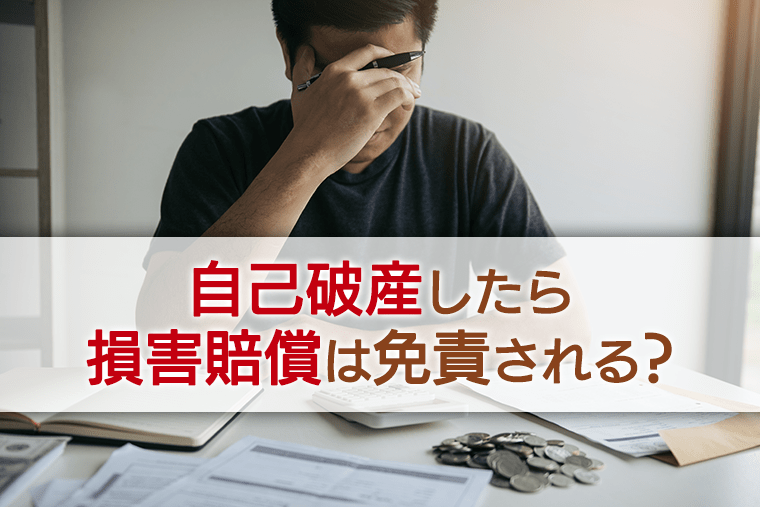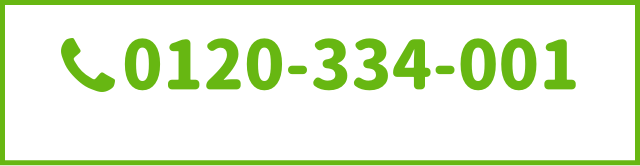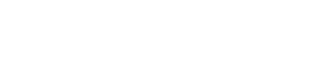仮想通貨による借金は自己破産で解決できる?

仮想通貨への投資は、かつて「億り人」などという言葉を生み出して話題になりました。
その後取引所が破綻するなどして価値が暴落し、そうかと思うと2021年初頭には仮想通貨の1つであるビットコインが再び史上最高値をマークするなど、相場の乱高下がたびたび取り沙汰されています。
当たれば大きく、外れれば大損をするかもしれないのが仮想通貨取引です。
もし仮想通貨の取引で借金を背負ってしまった場合は、どうにかして借金を解決するしかありません。
借金解決方法として、「自己破産」や「個人再生」などの債務整理方法が用意されています。
しかし、仮想通貨取引による借金を債務整理することはできるのでしょうか?
この記事では、そういった疑問に答えていきたいと思います。
1.仮想通貨の債務は「借金」と「税金」の2つ
仮想通貨で債務を背負ってしまう理由は主に2つです。
- 仮想通貨の取引をする資金を得るために借金をして、投資に失敗して返済できない
- 仮想通貨取引で儲けたけれど、それによって発生した多額の税金を支払えない
しかし「借金」と「滞納した税金」には大きな差があります。
「借金」は債務整理をすることで解決ができますが、「税金」は債務整理をしても直接解決することはできません。
例えば債務整理の1つである自己破産は借金をゼロにする効力を持っていますが、自己破産をしても税金に関しては支払義務が残ります。
借金を減額できる債務整理である個人再生でも同様に、滞納した税金の減額はできません。
滞納した税金を解決するには、徴税者である行政側の担当部門に行って相談し、分割払いなどを認めてもらう必要があります。
「未払いの税金」と「借金」を両方抱えている場合、借金を債務整理で解決すれば、税金を支払う余裕を生み出せるかもしれません。
2.仮想通貨の「借金」解決方法
ここからは税金ではなく、民間企業から借り入れた借金の解決について解説していきます。
何度も出ているように「債務整理」をすることで借金は解決できますが、債務整理にも種類があります。
債務整理の効果について簡単に見ていきましょう。
(1) 任意整理
債権者と交渉して、遅延損害金や将来発生する利息をカットしてもらいます。
その後は支払いスケジュールを調整し、借金を分割払いしていく旨の合意を取ります。
他の債務整理と違って裁判所を介さないので早く手続きが終わりますが、減額効果が少ないという欠点があります。
基本的に元本部分は減額されないので、借金の額が大きい場合は焼け石に水となる可能性が高いですし、そもそも交渉がまとまらないこともあるでしょう。
(2) 個人再生
裁判所に申立てを行って、借金を大幅に減額してもらう債務整理です。
元本の部分が減額され、減額率は最大で90%にもなるため、借金が一気に10分の1の額になることもありえます。
しかし、軽減されたとは言え借金が残るので、それを支払えるだけの定期的な収入が将来にわたって継続する見込みがなければ、裁判所が個人再生を認めてくれません。
さらに借金総額が5000万円を超えると、そもそも個人再生という制度そのものを利用できません。
手続きも複雑なので、利用の際は債務整理に詳しい弁護士とよく相談してください。
(3) 自己破産
裁判所に申立てを行って、借金をゼロにしてもらう債務整理です。
減額効果だけを考えれば最強の債務整理ですが、自己破産をすると自分の財産が一部を除いて全て処分されてしまいます。
当面の生活に必要な現金や家具家電類などは処分を免れますが、不動産などの高価な財産は手放すことになるでしょう。
自己破産については別の項目で解説していきます。
自己破産で処分される財産は、有形無形を問いません。保険の返戻金やまだもらっていない退職金といったものまで、換金性のあるものは幅広く処分されます。
この理屈に従えば仮想通貨も処分の対象になるのですが、現実的に仮想通貨を処分するのは難しいとされています。
仮想通貨を換金するには秘密鍵やパスワードが必要となるため、破産者の協力が不可欠です。破産者が協力に応じなければ、事実上換金できないことになります。
しかし2019年11月に大阪府寝屋川市が市税滞納者の仮想通貨を、全国の自治体として初めて差し押さえた事例があります。この滞納者は仮想通貨を仮想通貨交換会社に預けており、自治体は交換会社に預けていたものを差し押さえたそうです。
差し押さえと自己破産による財産処分という違いはありますが、今後自己破産においても何らかの方法で仮想通貨の処分が可能になるかもしれません。
少なくとも現時点(2021年2月上旬時点)では、破産者の協力なしに自己破産手続きで仮想通貨を処分することは難しいようです。
ただし、破産者には破産手続に協力する義務があり、協力を拒めば免責に影響が出る可能性がありますから、裁判所や管財人から処分に協力するよう求められれば協力する必要があります。
3.仮想通貨による借金は自己破産できるか
任意整理や個人再生では対応できず、自己破産をすることになったとします。
はたして仮想通貨取引による借金でも、自己破産はできるのでしょうか?
実は、自己破産できる条件の1つに「免責不許可事由に該当しないこと」というものがあります。
免責不許可事由は破産法に記載されていますが、ここでは代表的なものを説明します。
- 借金の原因が浪費やギャンブルまたは射幸行為である
- クレジットカードのショッピング枠を現金化した
- 既に返済不能な状態にも関わらず、それを偽って金銭を借りた
- 特定の債権者にのみ有利になるような弁済をした
- 自己破産をするための費用にするため借金をした
- 自己破産のために裁判所に提出する書類に虚偽の事実を記載した
- 財産を隠匿する、または不当に安値で処分した
- 裁判所の自己破産手続きに対して誠実に協力をしなかった
仮想通貨取引において問題になるのは最初の一文です。
仮想通貨取引は「浪費やギャンブルまたは射幸行為」に該当するとされているため、これによる借金は免責不許可事由に当たるのです。
もし免責不許可事由が厳密に運用された場合、仮想通貨取引による借金では自己破産できないことになります。
しかし、破産法には「裁量免責」というものが認められています。
これは「免責不許可事由があっても裁判官の裁量で借金をゼロにできる」というものです。
パチンコなどの借金で自己破産する人が毎年一定数いますが、射幸行為であるパチンコでの自己破産が認められているのは、この裁量免責があるためです。
裁量免責を得られるかどうかの基準は裁判所によって違うので、自分の居住地を管轄する裁判所の運用に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
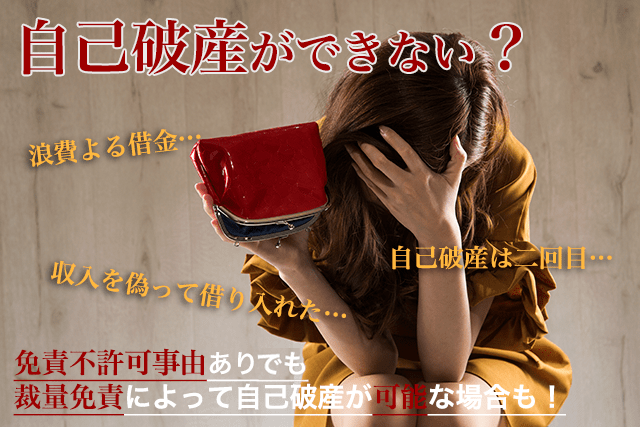
[参考記事]
免責不許可事由とは?該当しても裁量免責で自己破産ができる!
4.仮想通貨取引による借金は債務整理で解決できる
滞納した税金は債務整理で解決できませんが、借金は債務整理で解決可能です。
借金が過大で返済不能であれば自己破産がおすすめですが、自己破産には免責不許可事由というものがあります。
仮想通貨取引による借金は免責不許可事由に該当するため、裁量免責をうまく勝ち取れるかがポイントになります。
裁量免責を得る基準やコツについては、債務整理に詳しい弁護士にご確認ください。
弁護士なら「裁量免責を取れそうな案件か?」「どうすれば裁量免責を取れる可能性が上がるか?」を真剣に考えて、そのための手段をアドバイスしてくれます。
「仮想通貨の取引は自己責任だから諦めるしかない」と考えずに、借金のお悩みはなんでも弁護士までご相談ください。