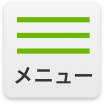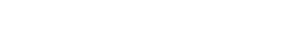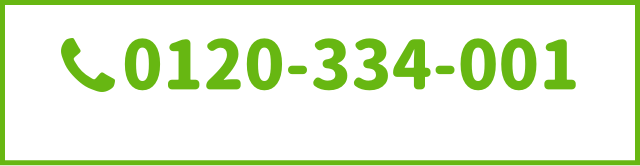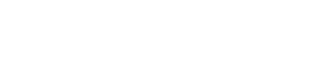個人再生中の退職・転職は可能?
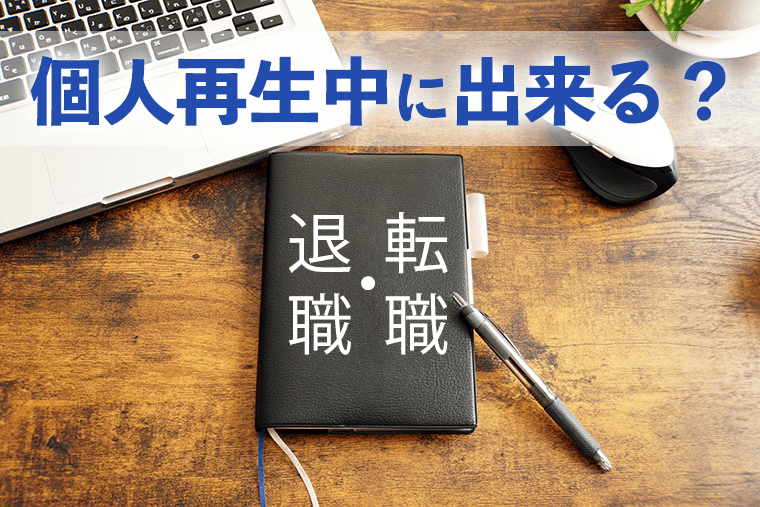
個人再生では、手続後に最低でも3年間は借金返済を続けていかなければなりません。そのため、その返済を確実に継続できるよう、厳しい収入要件が必要とされます。
すなわち、収入が足りていない・収入に断続性がないと判断されたら、借金の減額を認めてもらえなくなるのです。
では、個人再生している最中に転職や退職をすることはできるのでしょうか?
1.個人再生の要件「継続的・反復した収入」について
個人再生は借金を大幅に減額できる制度ですが、認可にはいくつかの要件をクリアしなければなりません。
その中でも重要なのが「債務者が継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」という点です(小規模個人再生の場合。給与所得者等再生の場合は要件が更に厳しくなります)。
個人再生認可後は原則3年(例外5年)で完済し、その間は2~3ヶ月に1回程のペースで残債を返済します。
よって、裁判所に個人再生を認可してもらうには、再生計画通りに返済できる見込みがあることが大前提となります。
(※実際には、借金総額と収入額、毎月の家計収支などにより総合的に判断されます。)
サラリーマンなどのように毎月月給が入ってくる場合は、安定性ということに関しては問題になりません(返済できるだけの収入があるかどうかが焦点になります)。
一方、自営業の場合は、月によって収入の差があるためサラリーマンより安定性には欠けますが、約3ヶ月に1回の支払いに支障がないと判断されれば認可される可能性は高くなります。
アルバイト、パートの場合は、雇用期間が不安定なので、将来に渡ってその収入が安定的に確保されるとは限りません。しかし、同じ職場で長期間継続しており、収入も安定しているというケースでは個人再生を利用できるでしょう。
アルバイトやパートの方、専業主婦、無職の方の個人再生については以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
個人再生はアルバイト、専業主婦、無職でもできる?
2.個人再生中の転職・退職の可否
個人再生では、開始時に継続的・反復して収入を得る見込みがないと判断された場合は、そもそも手続きの開始が認められません(棄却)。
また、再生手続途中に状況が変わり、収入を得る見込みがなくなかったと判断された場合、認可の審査前に再生手続は廃止(打ち切り)されます。
個人再生手続が終わり返済期間がスタートしている場合でも、転職や退職により返済が滞ってしまえば再生計画が取り消されてしまう可能性があります。
このように、全体を通じて継続的又は反復的な収入があることが必要となりますが、個人再生中に退職や転職をするとどのような影響が生じるのでしょうか?
(1) 転職の場合
転職は、個人再生の申立期間中も返済期間中も可能です。返済できる収入が引き続き確保されるのであれば通常問題にはなりません。
しかし、以下のような点に注意が必要です。
- 申立期間中:転職により収入が変わるので、書類内容の変更・追加をする必要があります。それだけ手続きに時間がかかるので、認可まで時間かかる可能性があります。
- 返済期間中:転職したことで収入が下がり返済ができなくなった場合、個人再生は失敗します(やむを得ない事情による場合は、返済計画を2年延長して毎月の支払額を減額してもらえることもありますが、認められるかどうかはケースバイケースです)。
個人再生中に転職する場合は、弁護士に相談してから行動することをおすすめします。
転職により退職金が出る場合は要注意です。個人再生には「清算価値保証の原則」があり、退職金がある場合には弁済額が高くなる可能性があります。
清算価値とは、債務者の全ての財産を処分して現金にした価値のことです。個人再生では債権者の権利を守るため、清算価値以上の弁済をすることを認可の条件にしています。そして、退職金の一部もこの清算価値に含まれる財産とみなされます。
退職金の清算価値が計算されるタイミングは、個人再生の認可決定時と考えられるので、それ以前に退職の確定、退職金の受領はしないなどの工夫が必要になります。
参考:退職金は個人再生の減額率に影響するのか?
(2) 退職の場合
退職についても、申立期間中でも認可決定後の返済中であっても可能ではあります。
しかし、退職をすると収入がなくなるので、再生計画の審査が通らなくなる可能性が高いです。
また、認可決定後だとしても、収入がなくなれば返済できずに再生計画の履行に失敗するリスクがあります。
(※また、転職と同様に退職金が清算価値にプラスされるので、認可決定前に退職を決定したり退職金を受領したりすると、弁済額が上がる可能性が高くなります。)
とは言え、リストラや事故・病気など、やむを得ない事情で退職をしなければならないときは、返済計画を2年延長することが可能かもしれません。
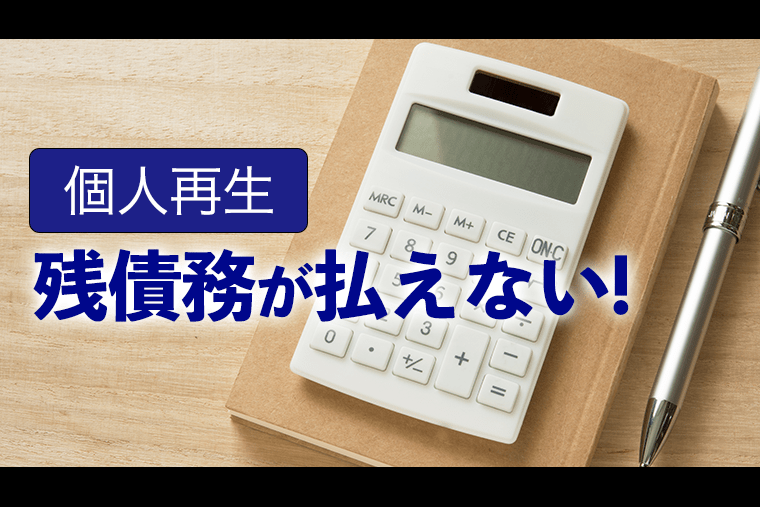
[参考記事]
個人再生後の残債務を払えない!支払い遅れは待ってもらえる?
個人再生後に収入の状況が変わった場合は、状況が行き詰まる前に速やかに弁護士に相談をしてください。
3.まとめ
以上のように、個人再生中に退職も転職もすることはできます。
しかし、特に退職については慎重に行わなければ、個人再生が失敗してしまう可能性があります。
個人再生をするなら、泉総合法律事務所にご相談ください。棄却・廃止・不認可を避け、個人再生を成功に導くために全力でサポートいたします。