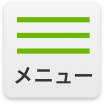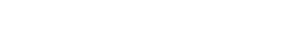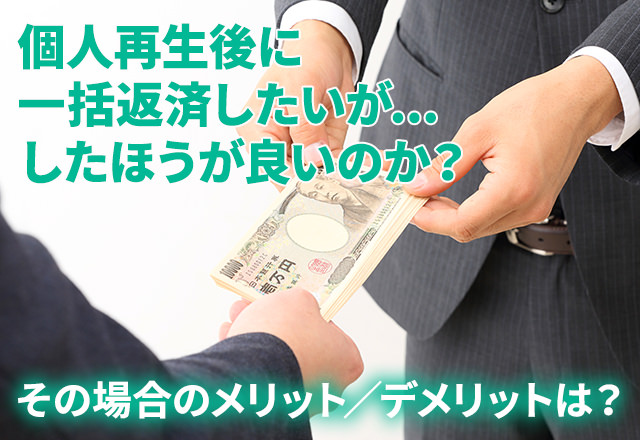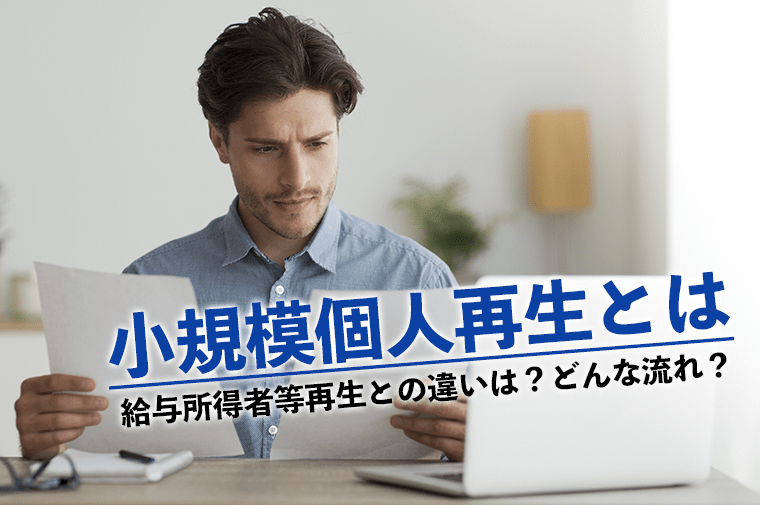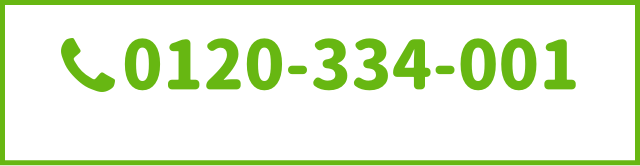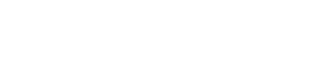個人再生でいくら借金が減る?減額率の決定方法を解説

個人再生では、裁判所の認可を得た上で債務額を元本から大幅に圧縮してもらいます。
では、借金の減額率はどのように決定されるのでしょうか。
結論から言えば、100万円以上、5,000万円以下の借金であれば借金は大幅に減額されますが、減額率は一律ではありません。「どれだけ借金を減らすか」という割合は、まずは法律において債務額に応じて決められており、借金の額が多いほど減額幅も大きくなります。
しかし、他に検討する要素もあるため、複数の個別事情を見て減額率に予測を立てる必要があります。
1.個人再生手続きの流れ
冒頭の通り、個人再生後の返済額を決定する最も重要なポイントとなるのが「借金がいくらあるか(借金の総額)」です。
このため、債権の調査は裁判所によって慎重に進められます。
個人再生認可までの流れは以下の通りです。
(1) 個人再生の申立て
個人再生手続きをするときは、最初に裁判所に対して個人再生の申立をします。
申立書類を準備するのは非常に手間がかかるため、弁護士に依頼をして申立書類の作成を行ってもらうことをお勧めします。
(2) 個人再生手続開始決定
裁判所に提出した書類に不備がなく、手続き開始のための要件が揃っていると確認できれば、直後に個人再生手続きが開始決定となります。
なお、個人再生により減額された借金を将来的に支払えるのかどうかの判断も考慮されるので、開始決定を下してもらうには安定的で継続的な収入があることが前提です。
(3) 債権届出・債権調査
個人再生手続きが開始されると、債権者に対して開始決定の通知が出されます。
債権者は通知の内容を確認した上で、指定の期間内に自分がどんな内容の債権をどれだけ持っているのか、裁判所に届出を行います。これを債権届出と言います。
債権者から提出された届出は、裁判所によって債務者(または代理人弁護士)に渡されます。ここでもう一度債権調査を行い、借金の金額を確定します。
(4) 原則3年間で分割返済する再生計画案を作成
債権額が確定したら、その内容に基づいて再生計画案を作成します。
個人再生では、原則、認可決定後3年以内に減額後の借金を完済しなければなりません。ただし、特別の事情がある場合、最長5年まで延長することが可能です。
弁護士と一緒に検討すれば、無理なく完済ができる再生計画案を作成できるでしょう。
(5) 再生計画案に対する裁判所の認可
再生計画通りに返済を行うことができるだろうと判断された場合は、裁判所が再生計画案を認可します。
認可後は再生計画通りに返済を行います。大抵は決定の翌月から返済が始まるのが一般的です。
なお、小規模個人再生という手続きで個人再生を進める場合、債権者の半数以上、または債権総額全体の1/2を占める債権者の同意が必要です。
2.個人再生の最低弁済額について
個人再生は、借金を大幅に減額して経済的な再建をはかる制度です。
しかし、減額すると言っても際限なく借金を減らすことはできません。
最低限度支払わなければならない額は法律で定められており、その基準を定めたものが「最低弁済額」です。再生計画の返済額はこれを下回ることはできません。
債務総額に対する最低弁済額は以下の通りです。
| 債務総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 債務総額(減額無し) |
| 100万円以上、500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上、1,500万円未満 | 債務総額の1/5 |
| 1,500万円以上、3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超、5,000万円以下 | 債務総額の1/10 |
例えば、債務総額が2,000万円のとき、上記の基準に照らすと最低弁済額は300万円になります。
ただし、債務者に不動産・車・預貯金などの高価な財産があり、この財産の総額に300万円を上回る価値がある場合は、清算価値保証の原則によりその所有財産の額が最低弁済額となります。清算価値とは、「仮に自分の財産をすべてお金に換えたらいくらになるのか」を算出したものです。
上記の例で言えば、例えば車と土地を持っていて、それらの財産価値が400万円になる場合、弁済額は300万円ではなく400万円となります。
これは、借金を減額される債権者の利益を最低限確保するためのものです。
なお、債権者の半数以上の同意が得られずにやむを得ず給与所得者等再生で個人再生手続きを進める場合、「可処分所得」が最低弁済額になることもあります。
可処分所得とは、税金や社会保険料等を引いた債務者の手取り収入から、さらに「債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な費用」を引いた金額です。
3.まとめ
このように、個人再生では、主に借金の額によって弁済額が異なってきます。
弁済額の決まり方はケースバイケースですが、いずれにせよ元本から大幅に借金を圧縮できますので、個人再生をするメリットは大きいと言えるでしょう。
しかし、個人再生手続きは書類も多く、債権の評価も複雑で、再生計画を有利に進めるには専門家のサポートが必須です。
泉総合法律事務所は個人再生の実績が豊富な事務所です。債務整理を得意とする弁護士が、お1人お1人の状況に合わせてベストの解決法をご提案します。
債務整理をご検討の方でしたら、ご相談は無料で行っております。借金のことでお困りならばどうぞお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。